第二回 我が時代
福地 英明(短距離)
64期(2010年3月卒業)

ついこの前まで桐朋生だった私に依頼が来た時には正直びっくりしましたし戸惑いました。しかも菊地さんと違い表立った活躍をあまりしていない私が書いて果たして後輩の役に立つのか、そしてこのページを楽しみにしておられる諸先輩方に対して失礼にならないのか、色々考えましたが外堀先生の「是非福地にお願いしたい」というお言葉と同期主将である丸山の「福地が書いて誰かが文句を言うはずがない」という言葉に励まされ筆をとりました。(ちなみに文章の形式は菊地さんの物を参考にさせていただいております。) 上手い文章が書けないことは分かっていますが「普通のレベルの人が何を考え練習・試合に臨んでいたのか」が少しでも後輩に伝われば、この文章を書いた者としてそれに勝るものはありません。 。
自己紹介
挨拶代わりに自己記録を…
100m:11”25 (+0.5)
200m:22”39 (-2.5)
300m:38”3
400m:50”75
見ればわかりますが私は個人で桐朋記録はつくっておらず、またそのレベルに達してもいません。「そのような人間がどのようにモチベーションを保ったのか」を以降書きたいと思います。
入部まで
私はインドア派の人間で、中学に入ったら化学部に入ろうと思っていました。しかしながら中学1年生のスポーツテストの時にクラスで1番速く、「陸上でもイケるかも」という軽い気持ちで入りました。(ちなみに、入った当初は気付いていませんでしたが、私がクラスで1番になれたのはそのクラスが足の速くない人が集まったクラスだったからなのです。)そのスポーツテストの記録は14”9。おそらく学年で30番程度だったと思います。
中学時代
中学生時代ははっきり言って全く活躍できませんでした。当時活躍していた同期の丸山や佐伯・和泉をはじめとする後輩たちを羨ましく思う一方で「どうせ自分はあのレベルになる才能がない」と決めつけ、練習をよくサボったり合宿に行かなかったりとかなりいい加減な短距離ブロック長でした。そのようなブロック長でしたので当時中学キャプテンをしていた丸山と意見の相違から言い争いになることもしばしばあり、部の雰囲気はあまり良いものではなかったよう思います。そんな中、中学都総体(後述)が契機となり陸上競技に本格的にのめり込んでいきました。ただ、どうしても後輩で同じ短距離を専門とする佐伯に勝つことができず、悔しい思いをしていました。
高校時代
高1の頃は大久保先生の指導の下、短距離のメニューを淡々とこなしていました。が、高2になり「淡々とこなすのではなくより能動的にこなさないと意味がない」ということに真剣に気が付き、練習ノートを真剣に書き留めるようになりました。また、高2になり、400mリレーの中心的な存在となりました。この頃のベストメンバーは福地・飯島・和泉・佐伯の4名でしたが飯島や和泉の怪我、跳躍と短距離の練習環境の相違(短距離は大久保先生の管轄下であり跳躍は外堀先生の管轄下)により丸山や1つ上の澤先輩をメンバーに入れることも多く、バトンパスの練習時間がほとんどとれない、というのが現状でした。その後、当時の高3生が引退すると、もはや短距離だけではリレーのメンバーを作れなくなり、言わば「跳躍から選手を借りる」状態が続きました(後述)。高2のシーズン終了後、私のリーダーシップ力不足もあり、メンバーの一人が「もう走りたくない」と言い出し一時期は空中分解寸前までになってしまいました。結果的にそのメンバーはリレーを走ることに納得し、また、短距離ブロック長である私と跳躍ブロック長である丸山が連携して積極的に跳躍にリレーの練習に参加するよう呼びかけた結果、十分な練習時間を確保できた状態で高3のシーズンを迎えられました。私の個人の能力では南関東にすらたどり着けないことは目に見えていたので、高3の初めには「専門ヨンケー」と言っておりました。結果はさておき(後述)400mR・1600mRともにベストメンバーでベストなコンディションで、なにより皆で一体感を感じながら走ることができたことは1メンバーとしてそしてリレーチームを引っ張ってきた人間として大変うれしかったのを記憶しています。
総括
以上のように、陸上競技という個人スポーツでありながら、思い出すのは仲間との一寸したやり取りだったり皆との一体感だったり…と陸上がある種の「チームスポーツ」であることを強烈に感じた高3でした。感覚の面だけではなく、実際の練習に於いても「練習で手を抜いてリレーメンバーの仲間に迷惑をかけたくない」というのが最大のモチベーションになっていたことからも陸上がチームスポーツだと確信していました。
しかしながら中学生時代の僕のように同期の成績を羨ましく、時には疎ましく思う人もいるでしょう。そのような人はこの言葉を頭の片隅に入れて置いてみて下さい。それは丸山が残した言葉でありますが、尤もだと思ったので引用します。
「厳しい練習に耐え、漸く勝ち取った成績よりも、支えあいながら、切磋琢磨しあいながら、一緒に練習してきた仲間の方が遥かに大切です。」
現役の陸上部員の皆さんは結果主義の残酷な世界で生きているので羨ましく思うこともあるのです。けれども、引退後は陸上の成績に関わらず「キツい世界を共に歩んだ同志」であるわけなので、きっとその結束力は素晴らしいものがあると思います。縦横斜めの結束力を大切にして、皆さんが切磋琢磨し、あらゆるレベルの志を持った少年が気兼ねなく入れる雰囲気を受け継いでくれたらそれに勝るものはありません。
思い出の試合
皆さんの何らかの参考になれば幸いです。(時系列ごとに並べました)
予選は私の代わりに丸山が走っていましたが彼は直前の400mHで疲れきってしまい、急きょ私が走ることに。それまでラップは53秒台でしたが、「チームのみんなに迷惑はかけられない」と奮起した結果なんと50秒台で走ることができました。私のマイル本メンバー入りはこの瞬間に決定しました。
1年以上23"0の壁を越えられずにいた私でしたが焦らず腐らず努力したのが実った試合でした。また初めて後輩に勝つことができた試合としても記憶に残ってます。
桐朋記録&関東大会を狙っていた試合だっただけにゴールすらできなかった時はさすがに辛い気持になっていました。さらに飯島と和泉は転倒によって怪我をし、このシーズンを棒に振りました。私にとって「最も嫌な試合」となってしまいました。
皆の足手まといにならないようにということだけ考えた試合でした。結果は4位!!マイルも関東レベルに上がっていることを感じ、とても興奮しました。
個人競技ではあきらめていた私でしたが「リレーチームの為に個人走力を上げる」というモチベーション維持により、結果的に個人能力を上げることに成功しました。陸上は団体競技であることを最も感じた試合です。
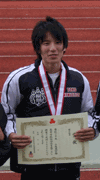
表彰式での様子
4×100mR(和泉・飯島・福地・丸山)
予選 42”68
組3位でゴールした瞬間は「都大会のようにまた勝ち上がるのではないか」と期待していた私たちでしたが、敗退が決定した瞬間は頭が真っ白になってしまいました。しかも結果が0.02秒足らずに9位であったことを知った時にはマイルに頭を切り替えることがなかなかできませんでした。ただ、あのメンバーであの舞台をあの気持ちで走ることができたのは一生の思い出です。
この種目に全てを賭けることにした私は「専門外だとか言っている場合ではない」と腹を括りました。17~18秒が決勝のラインだと言われていたので、私たちの持ちタイムからすると結構厳しい戦いであることはわかっていました。私も精一杯努力し、48秒台で周りましたが(2+2)で決勝進出チームを決める予選で組5位であることがわかった瞬間に頭が真っ白になってしまいました。そしてその記録は同時に全体5位、つまり他の組の1位よりも私たちの方が速かったことを知った時には唖然としてしまいました。
終わりに

桐朋高校は09年度に都大会総合2位に輝きました。詳しいことはいつの日かキャプテンである丸山に書いてもらうとして、私が後輩に言いたいのは「高い目標を持て」です。これは経験則ですが、目標は(無謀では無意味ですが)限界よりもちょっと上に設定することが最もベターなのではないかと思っています。私たちOBは後輩の活躍を期待していますしそれが何よりの楽しみでもあります。次回は長距離を専門としていた人に書いてもらう予定です。ご期待ください。
P.S. 菊地さんの文章を勝手に参考にさせていただきました。ありがとうございました。菊地さんは現在僕が所属している陸上同好会の先輩でもありますので今後もよろしくお願いします。




